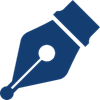2025年5月12日、金融庁より保険会社向けの監督指針の改正案が公表されました。
また同時期に、保険業法の一部を改正する法案も国会で審議されており、今国会中の可決が見込まれています。
これらの改正は、一見すると「保険会社の話」に見えますが、実際にはその矛先は明確に保険代理店の管理体制・販売姿勢・情報管理のあり方に向けられています。
つまり、今回の改正は、保険代理店にとっても無関係ではなく、むしろ事業の継続性そのものに関わる重要な転換点なのです。
■ 「モニタリング強化」=保険代理店選別の本格化
今回の監督指針案では、保険会社に対し、代理店の体制整備状況を“実質面”で継続的に把握することが求められています。つまり、表面的な帳票提出だけでなく、次のような点が重視されることになります。
○苦情や違反の再発防止策が、実際に機能しているか
○教育・点検が記録され、改善につながっているか
○経営者が現場の課題を把握し、主体的に対応しているか
こうした実態が不十分であれば、“リスクが高い保険代理店”と判断され、保険会社との関係に見直しが入る可能性が現実味を帯びてきます。
■ 情報管理体制の甘さが、保険会社の“撤退判断”を呼び込む
とりわけ金融庁が注目しているのが、保険代理店の情報管理体制です。
「紙の管理はしている」「PCにパスワードはかけている」――それだけでは不十分です。以下のような実態が見られる代理店は、即座に改善が求められます。
○退職した社員のID・アカウントが削除されず放置されている
○顧客情報や業務データが、私用端末や無料アプリに保存されている
○情報漏えい時の初動対応フローが整備されていない
○IT(システム)管理責任者の名ばかり選任、委託先への管理監督がない
保険会社側としては、代理店の情報管理体制の不備があれば、自社のガバナンスリスクに直結すると判断し、契約見直しやモニタリング強化の対象にせざるを得ません。
これからは、“情報管理の甘さ”が、保険代理店の存続リスクを高める時代になってきたと言えるでしょう。
■ 「便宜供与」と見なされる販売関係・推奨姿勢にメス
今回の監督指針案では、「過度な便宜供与の禁止」にも明確に言及されています。
中でも注視すべきは、保険会社と保険代理店の関係性が、販売行動に不適切な影響を及ぼしていないかという点です。例えば、以下のような実態は“便宜供与の疑い”として見られる恐れがあります。
○特定保険会社から支援を受けている保険代理店が、その商品の販売を優先している
○比較説明を形式的に行いながら、実質的には特定の保険会社の商品だけを提案している
○意向把握と提案理由の整合性が取れていない
このような状況が続けば、保険会社側も監督責任を問われかねず、保険代理店との委託契約の継続を再検討する動機につながり得ます。
■ 今後、推奨販売は「お客様の意向を起点とした厳密な手続き」へ
さらに、現在審議中の保険業法改正案が可決された場合、施行規則の見直しにより、保険代理店の主観的な推奨販売は禁止される見込みです。
つまり、今後は「自社で選んだ商品を比較のうえ推奨する」販売スタイルから、「お客様の明確な意向を聞き取ったうえでの、合理的な商品選定」が必須となります。
また、契約が満期を迎えるお客様に対して、既契約の保険会社の商品を前提に推奨する募集のやり方はNGを突き付けられるため、逆にお客様がなぜ、既契約の保険会社の商品で継続・更新を希望するのか、明確な意向を確認、その理由を記録しておく必要が出てきます。
これは、比較推奨販売の考え方そのものの見直しであり、販売プロセスを一から再設計し直す必要がある保険代理店も少なくないはずです。
■ 最後に:選ばれる保険代理店になるために「今」動く
今回の改正の本質は、“どの保険代理店が信頼される存在として残っていくか”という、構造的な選別の始まりです。
逆に言えば、いま手を打てば、
「この保険代理店なら安心して任せられる」と評価されるチャンスでもあります。
✅ 情報管理ルールの棚卸し
✅ 推奨販売の業務プロセスの見直し
✅ 教育・点検・苦情対応の仕組みの再設計
✅ 契約先保険会社との関係の透明性確保
これらを一つずつ着実に見直すことで、**保険会社やお客さまにとって“選ばれる保険代理店”**へと進化していくことができるはずです。
当社では、保険代理店向けに顧問業務サービスを提供しており、顧問契約先には、体制整備に必要な各種の管理帳票や運用テンプレート、検証資料等を無償(定額制・スタンダードプランでのご契約の場合)で提供しています。
日々の業務で感じる課題や不安について、現場感覚に即した継続的な支援をご提供しています。
「うちの場合はどうだろう?」「まずは少し話を聞いてみたい」
そんな段階からでも、どうぞお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは、公式ウェブサイトのフォームより承っています。あらかじめご了承ください。