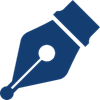「自分たちには関係ない」は通用しない ─ プロダクト・ガバナンス補充原則が保険代理店に突きつける現実
2024年9月26日、金融庁は「顧客本位の業務運営に関する原則」の改訂とあわせて、新たに「プロダクト・ガバナンスに関する補充原則」を公表しました。
これを受け、一部の保険代理店の間では、次のような声が聞かれます。
「うちは商品の組成なんてしていないから、関係ないだろう」
「プロダクトガバナンスって保険会社向けの話じゃないの?」
――しかし、それは重大な誤解です。
保険代理店も“販売者”としての説明責任が問われる
確かに、保険代理店は保険商品を設計・開発する立場ではありません。
しかし、補充原則の趣旨は「商品設計者と販売者が一体となって、顧客に適合する商品を提供せよ」という点にあります。つまり、販売者としての商品理解・対象顧客管理・販売方針の明確化が、保険代理店に厳しく求められるようになるということです。
金融庁は明確にこう示しています:
「商品を顧客に届ける経路(ディストリビューション・チャネル)においても、プロダクト・ガバナンスの趣旨を踏まえた運用が求められる」
つまり、保険代理店もプロダクトガバナンスの担い手であると、制度上明言されたに等しいのです。
現行の業務運営方針は、次の水準へ進化が必要
これまで「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、募集方針や対応方針を整えてきた保険代理店にとっても、プロダクトガバナンス補充原則は“次のフェーズへの移行”を求めています。
例えば、以下のような見直しが必要になります:
【1】商品理解と対象顧客の適合性の整理
○扱う保険商品ごとに、「どのような顧客に適しているか」「不適合なケースは何か」を、販売者視点で定義しておくこと。
○商品設計方針を把握し、それに整合した販売プロセスをとる努力義務。
【2】顧客属性と商品選定理由の記録
○「なぜその商品を提案したのか?」が、顧客属性との整合性から説明できる体制の整備。
○単なる意向把握ではなく、「その商品がなぜその顧客にとって最適なのか」の合理的な根拠の記録。
【3】販売方針・方針の開示内容の高度化
○「当社はこういう顧客に、こういう理由でこの商品を主に提案する」という販売戦略の明文化。
○方針と実際の販売内容の整合性を、定期的に自己検証する仕組みの導入。
「補充原則」は、保険代理店の業務品質が可視化される時代の起点
この補充原則は、単なる形式的な遵守の問題ではありません。
今後、損害保険業界に導入される「代理店業務品質評価制度」や、「自己点検チェック」との連動も視野に入り、保険会社との対話や手数料体系にも影響する可能性があります。
つまり、プロダクト・ガバナンスの視点での販売体制整備が、保険代理店の評価に直結する時代が、すでに始まりつつあるのです。
今、保険代理店が取り組むべきこと
このような時代の要請を踏まえ、保険代理店が今取り組むべき具体的なステップは以下の通りです:
| 取組項目 | 内容 |
|---|---|
| ① 商品ごとの販売方針の策定 | 対象顧客像、不適合事例、推奨理由を整理し、従業員との共有 |
| ② ヒアリング・意向把握様式の見直し | 商品との整合性を意識した質問設計へ改定 |
| ③ 記録保存と社内レビューの体制整備 | 販売実績との整合性検証と、改善サイクルの定着 |
| ④ 社員教育の強化 | 補充原則の内容や顧客説明責任の意識向上を図る |
まとめ:進化を迫られる保険代理店の役割
今回の改訂・補充原則は、保険代理店に対してこう問いかけています。
「本当に、顧客のためにその提案をしているのか?」
「その販売方針は、商品提供者の意図と合致しているのか?」
「お客様の利益を第一に考えた証拠を、第三者に説明できるのか?」
これは、制度対応というよりも、顧客からの信頼を得る“本質的な業務運営”への進化です。
プロダクト・ガバナンスの補充原則は、保険代理店の業務の質そのものを問う原則であり、商品提案における“説明可能性”と“透明性”が、今後ますます重視されていきます。
これまで誠実に顧客本位に取り組んできた保険代理店ほど、今回の改訂を真に生かし、他社と差をつける機会となるはずです。
私たちができる支援
当社では、顧客本位の業務運営マスターの資格を有する担当者が、今回の原則改訂や補充原則に対応した「顧客本位の業務運営高度化支援(取組方針の策定・取組結果報告書・対応関係表等の策定)」を行っております。
ご関心がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。